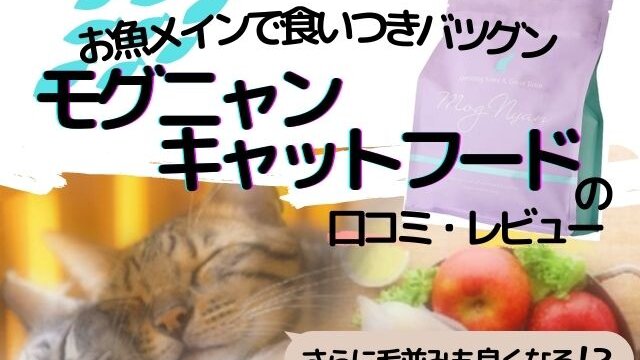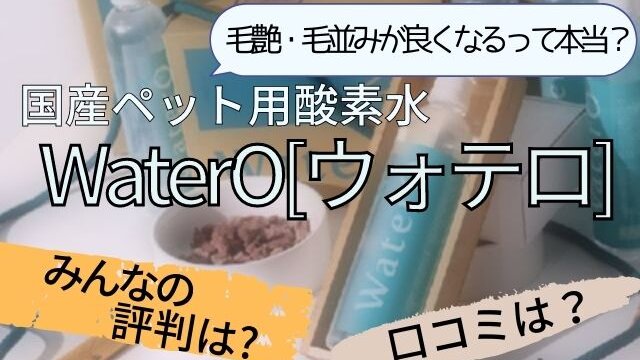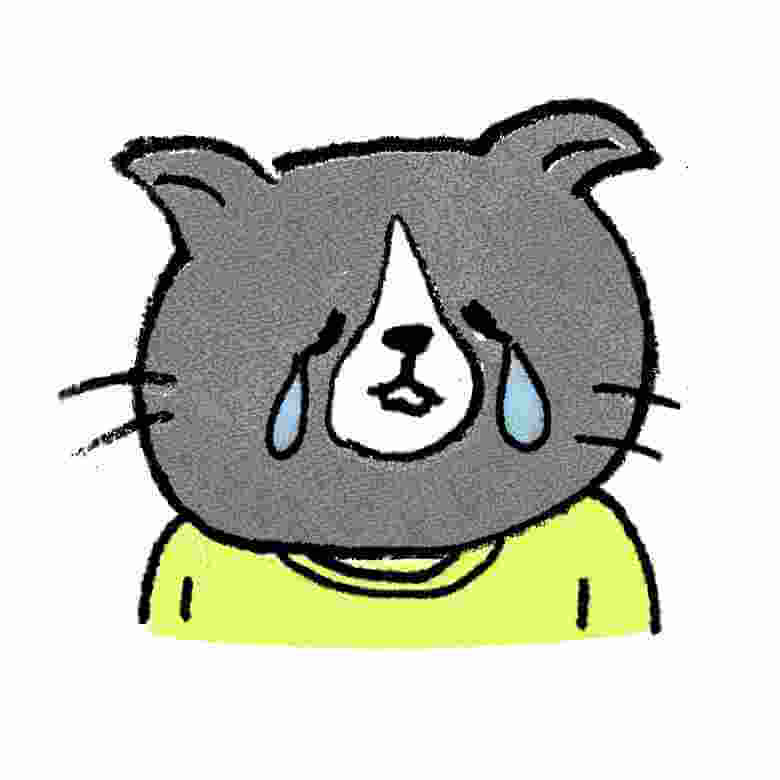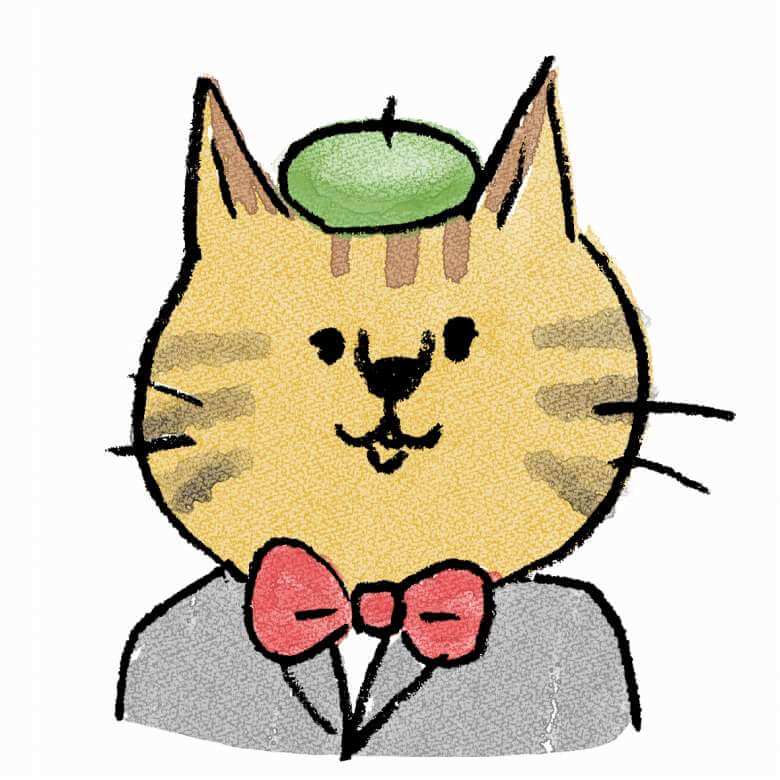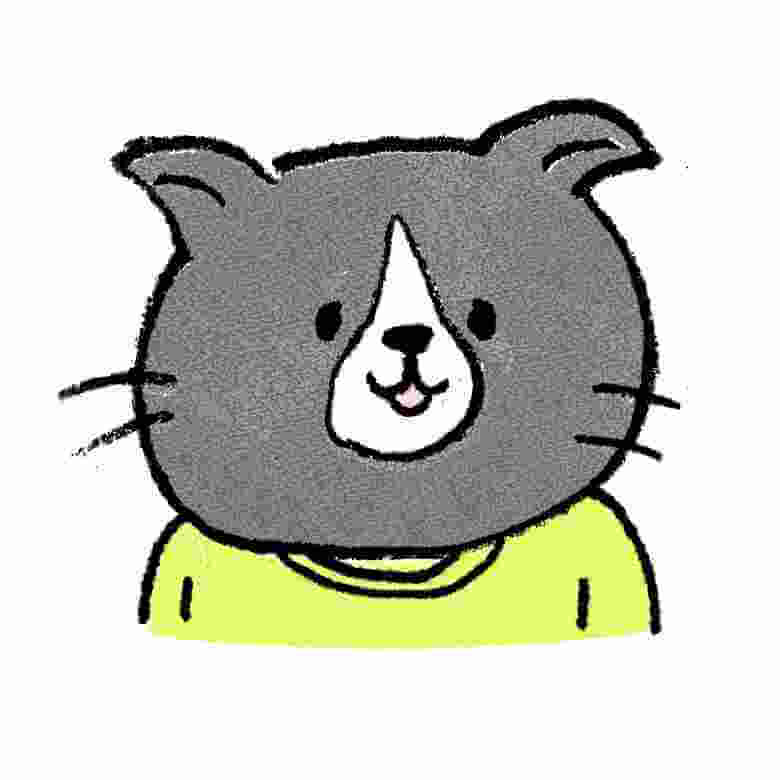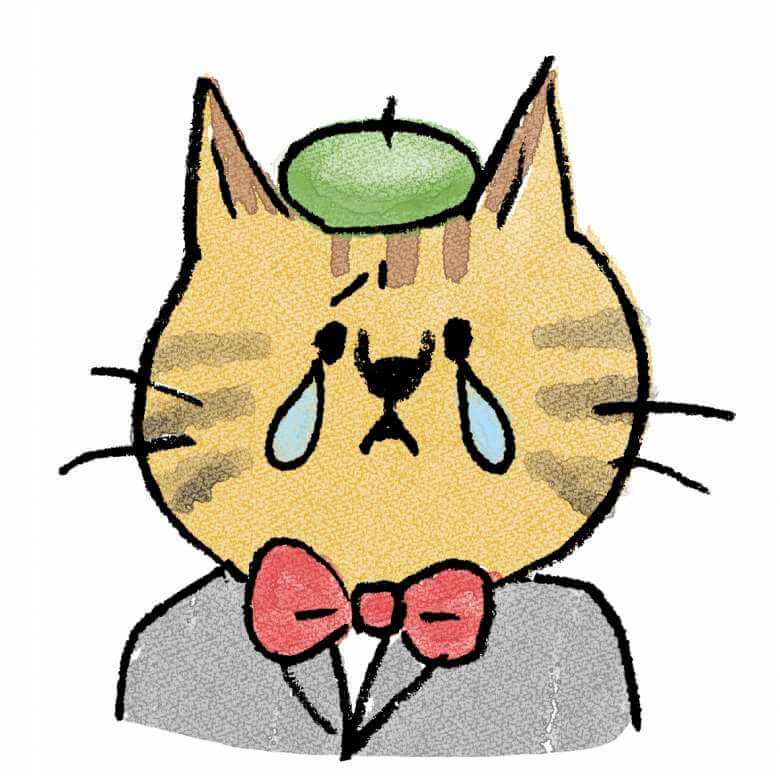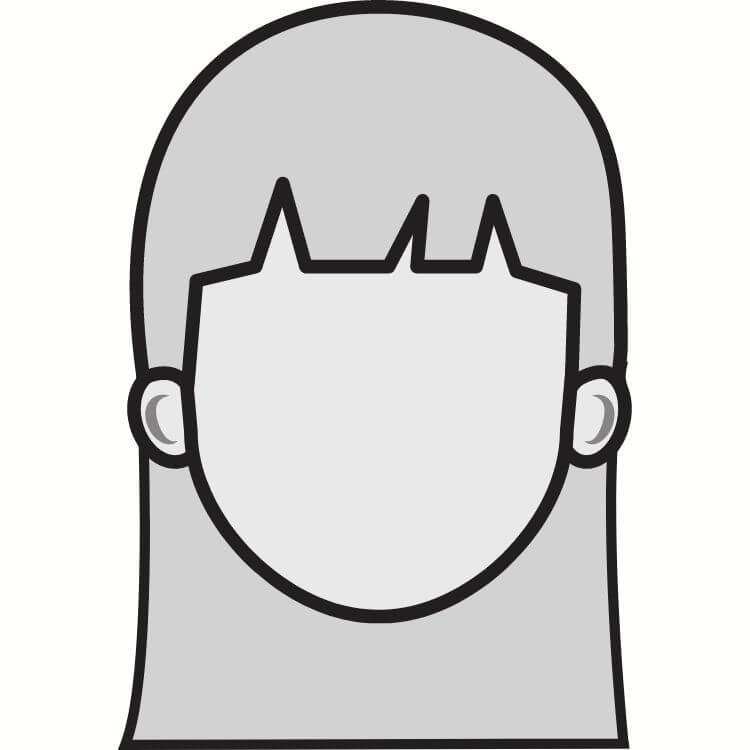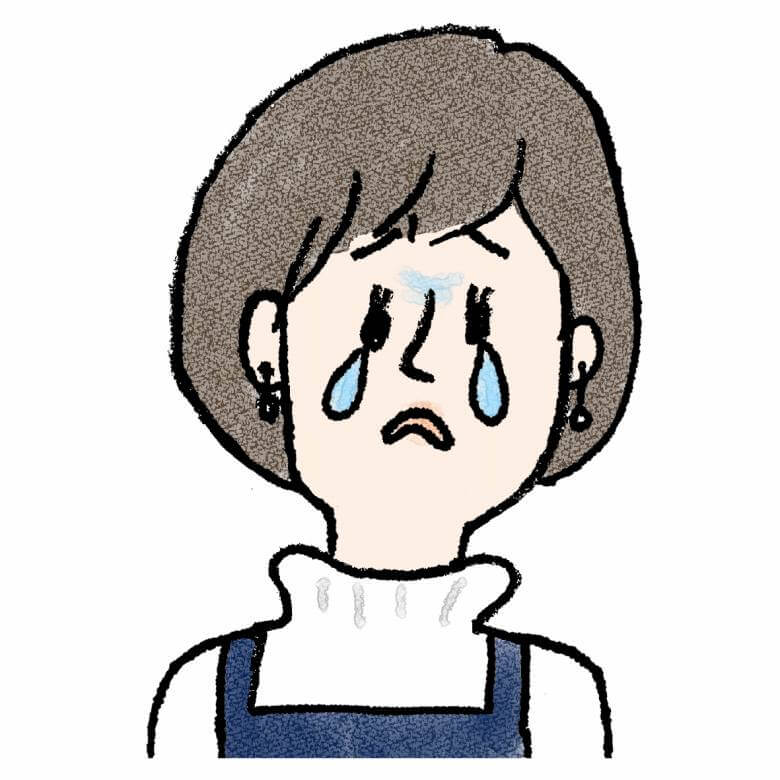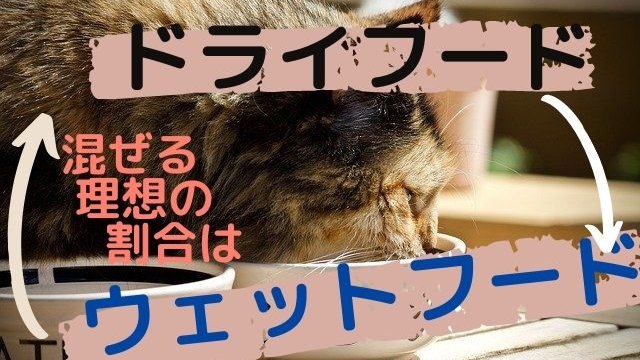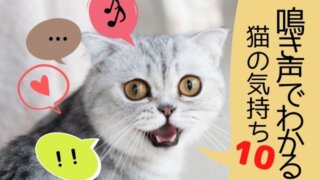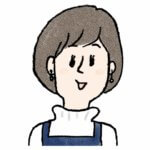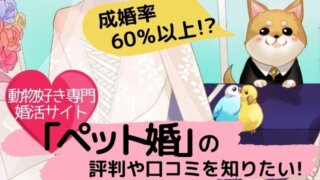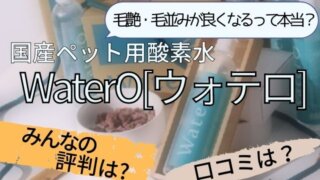先日、友人から「以前から猫の口臭がひどいなと思ってたんだけど、最近ご飯を食べなくなったから動物病院行ったら歯肉炎と言われた」と深刻そうに話をされました。
現在はお薬での治療が続いていて、少しずつ状態はよくなっていっているそうですが、餌は以前よりも食べなくなったとかなり心配な様子。
わたし自身、歯科衛生士をしていることもあり、猫の歯肉炎についても気になって、すぐに調べてみました。
調べてみて驚いたのは、3歳以上の猫のうち80~95%が、歯肉炎をはじめとした歯周病になっているといわれていること。
友人宅の猫ちゃんのように、愛猫が歯肉炎によってご飯を食べられなくなり、どうやって栄養をつけてもらえばいいのか、途方に暮れている飼い主さんも多いはず。
お口のトラブルで猫がご飯を食べなくなる経験は、わたしにもあります。このときはある秘策で無事乗り切ることが出来ました。
わたしの今までの経験も含め、今回は猫の歯肉炎と食事の関係を中心にお話ししたいと思います。
歯肉炎による口の痛みでご飯が食べられない猫ちゃんにご飯を食べてもらう工夫や、歯肉炎を予防するための食事について、情報盛りだくさんです。
歯肉炎とは、どんな病気なの?
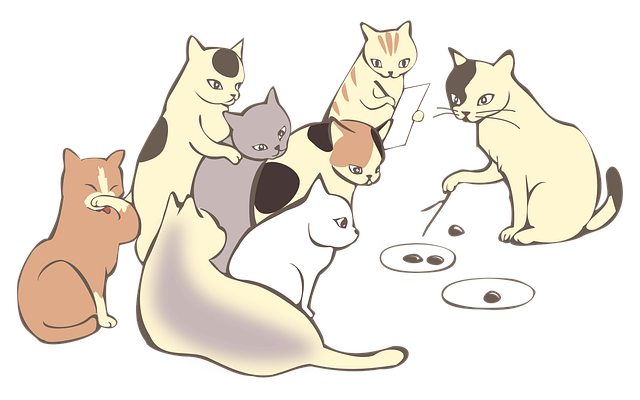
歯を支える歯周組織の病気を歯周病といいます。
その中の治療によって回復可能なものが歯肉炎、もとの正常な歯周組織に戻すことができないものが歯周炎。
今回は歯周病の初期段階でもある歯肉炎について詳しくお話ししていきますね。
歯肉炎になる原因
歯肉炎をはじめ、歯周病の原因は歯垢や歯肉、歯の隙間についた細菌です。
細菌が直接働きかける、もしくは細菌が出す毒素によって歯肉の炎症を引き起こします。
そこから、口腔内の衛生状態(歯がきれいか、傷がないか)、猫の免疫力や抵抗力の状態によって進行していきます。
- 歯についた歯垢や口腔内の細菌繁殖によるもの
- 口腔内の衛生状態が悪い
- 猫の免疫力の低下
歯肉炎の症状
歯肉炎は、最初に歯ぐきの表面部分が赤く腫れてくるところからはじまります。
放置すると、口腔内の痛みを感じるようになり、よだれが多くなったり、口臭がきつくなるなどの症状が見られる様に。
【歯肉炎の症状】
- 歯肉の発赤、腫脹
- 口の痛み
- 口臭がきつくなる
- よだれが多くなる
- 口や顔に触られるのを嫌がる
- 食事中、頭を傾けたり、片側のみで食べている
- 食欲がなくなる(食べる量が減る)
歯肉炎を放置してしまうと、歯周ポケットから膿がたまり、歯の根元にまで炎症を起こし、歯ぐきから出血したり、歯が抜け落ちてしまいます。
この状態になったものは歯周炎といい、元通りにはならなくなってしまうのです。
歯肉炎の治療法
歯石が付いている場合は歯石を除去するのですが、この処置は全身麻酔で行われることが一般的。
歯ぐきの炎症に対しては抗生剤やステロイド剤などを使いますが、病状が進んでしまっているという場合は、抜歯をすることもあるんですよ。
そのほかにも、状態に合わせて食生活の指導、基礎疾患(糖尿病、猫白血病など)の治療も同時に行っていきます。
歯肉炎をはじめ、歯周病については、こちらの記事で詳しく書いているのでぜひチェックしてみてください。
関連記事:【注意】猫は歯周病・口内炎が原因で死ぬ?!今日から始めたい予防法

また、病気になると猫の体のことはもちろん。10割負担である診療費も心配ですよね。
そんなときの備えとしてペット保険について、こちらの記事で詳しく載せているので、まだペット保険に入っていないという方は参考にしてみてくださいね。
関連記事:猫のペット保険はどうするべき?【比較が必要な理由と飼い主体験談】

歯肉炎でご飯を食べない時の5つの秘策
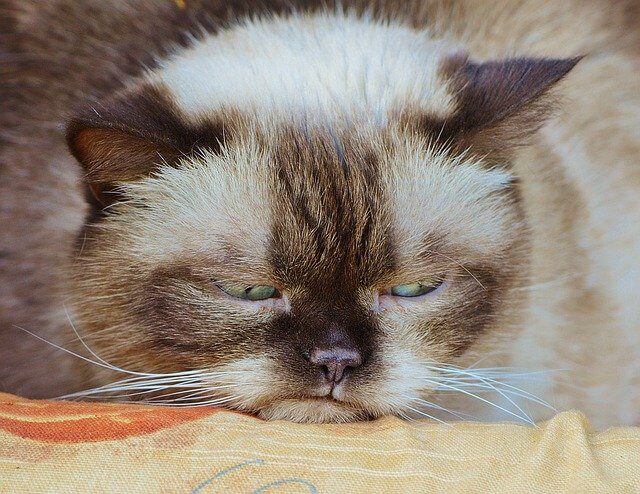
体調を整えるためはまずは栄養から。
そのため、食事は病気を治すためにも必ず必要なものです。
ここからは口が痛くて餌が食べられない猫ちゃんでも、ご飯を食べてもらう秘策を紹介していきましょう。
歯肉炎をはじめとした歯周病では、口の痛みに伴って食欲が落ちてしまうというのは先ほどお話しした通り。
そのため、食事はやわらかくて刺激の少ないものが良いとされています。
口の中の状態や栄養状態に合わせて餌の形や量を変えていくようにするといいですね。
1、ドライフードからウェットフードに切り替える
まず紹介するのは、普段のフードがドライフードの場合、ウェットフードに一時的に切り替えるという方法。
この後に詳しくお話しする予定ですが、実はドライフードは歯肉炎予防に効果的。総合栄養食としての形態でも多く発売されているので、普段の食事にドライフードを選ぶ飼い主は多いでしょう。
しかし、歯肉炎にかかっている猫は口の中の痛みで固いものが食べにくくなっています。
その点、ウェットフードは柔らかくて食べやすく、さらに水分を多く含んでいるので、餌と同時に水分補給も可能です。
水を飲むのも一苦労の状態の猫ちゃんにとっては、栄養と食事を同時にとることができ、メリットは十分あります。
普段の食事を変えたくないと考える飼い主さんもいるとは思いますが、ここは身体の調子を整える方が大切です。
また元気になってから、元のフードに戻してあげましょう。
関連記事:【猫が水を飲まない?】水を飲まない危険性と飲んでもらう為の方法!

2、ドライフードをふやかす
さまざまな理由で、簡単に餌を変えられない場合もあるでしょう。
また、猫は嗜好性の高い動物。
香りが高く、美味しいものなら食べる傾向にはありますが、中にはこだわりが強く、普段と違うものだとあまり食べないという猫も。
そんなときにおすすめなのが、普段のフードをお湯にふやかして柔らかくするというものです。
フードが柔らかくなるだけでなく、ふやかすことで香りが増し、猫の嗅覚を刺激して食事の喰いつきを良くする効果もあるんですよ。
わたしも以前飼っていたしゅりが軽い口内炎になって食欲が落ちた時、かかりつけの獣医さんからこの方法を教えてもらいました。
お湯の熱でフードの成分が変わったりするのではないかと気になったのですが、その獣医さんの話によると、熱湯じゃなければフードの成分が変質することは無いそうです。
しゅりにはその時ずっと食べていたフードをくたくたにふやかして食べてもらっていました。
その結果、しゅりはしっかりと餌を食べ、思っていたよりも早く症状が改善して、またすぐに元の固さのフードを食べられる様になったんです。
この方法はお金もかからず、すぐにできる方法なので、ぜひ実践してみてください。
3、好きなものの煮汁でフードをふやかす
これは先ほどの『お湯でふやかす』の応用版ですね。
お湯でふやかしたものを食べない場合、愛猫が大好きなもの。例えば、鶏肉やかつお節などの煮汁でフードをふやかすという方法があります。
ただし、ここで注意。人間用の出汁パックを使うのはやめましょう。
4、ふやかしたドライフードをウェットフードとまぜる
普段の食事から、ドライフードとウェットフードをまぜたものをあげているという飼い主さんもいるでしょう。
そのままのドライフードの場合だと、水分が多いウェットフードを混ぜているとはいえ、ドライフードの固さはそこまで変化がありません。
そのため、この場合もやはり、ドライフードはふやかしてあげることをおすすめ。
また、ドライフードをふやかしただけでは食べない場合も、ウェットフードを混ぜることで喰いつきアップに。
5、ミキサーなどで、餌をドロドロにする
人間の食事でも、歯がない人に対してミキサー食といって、完全に形を無くしてドロドロにしたものを勧める場合があります。
ひどい歯肉炎や口内炎の時は小さな粒でも刺激に。
猫の場合でも、ミキサーを使って、ドライフードとウェットフードをさらに食べやすい形にすることも可能です。
少し手間にはなってしまいますが、これも猫ちゃんを元の健康な状態に戻ってもらうための工夫ですので、ぜひ参考にしてみてください。
症状の改善がなかなか見られない場合や、食事を全くとってくれない時、体重減少が見られる時は早めに動物病院に行きましょう。
【歯肉炎でご飯を食べないときの5つの対処法】
- ドライフードからウェットフードへ変える
- ドライフードをお湯でふやかす
- お湯でふやかしたフードを食べないなら、猫の好きなもの(鶏肉、かつお節など)の煮汁でフードをふやかす
- ふやかしたフードをウェットフードとまぜる
- ミキサーを使ったり、すりつぶしたりして餌をドロドロにする
歯肉炎を予防する4つの方法

歯周病になってしまうことは、猫にとっては痛みだけではなく、食事もできなくなり、とてもつらいことなんです。
飼い主にとっても、苦しんでいる愛猫の姿はきっと見たくないと思われるでしょう。
予防1、ワクチン接種
歯肉炎の原因の中には、ウイルス感染症によるものがあります。これらのウイルスの予防をすることで歯肉炎になるリスクを減らすことができます。
- 猫免疫不全ウイルス(猫エイズとも呼ばれています)
- 猫白血病ウイルス(FeLV)
- 猫ヘルペスウイルス
- 猫カリシウイルス
以前、わたしの友人の猫が猫白血病になって亡くなってしまったのですが、その時はワクチンを打っていなかったそうです。
ワクチンで防ぐことができる病気に対しては、ワクチンを接種することが猫の健康を守るための最大の手段とも言えるでしょう。
猫のワクチン接種についてはこちらの記事でもご紹介しているので、お時間のあるときにチェックしてみてくださいね。
関連記事:子猫のワクチン接種はもう迷わない!【必要性や副作用を徹底解説】

予防2、歯みがき
歯肉炎をはじめとした歯周病の予防には、歯みがきが効果的。
最近では猫用歯ブラシの他に、歯磨き粉や口の中に散布するスプレータイプや液状歯磨き剤もあります。
歯みがきを嫌がる猫のために開発されたケア用品もありますので、この機会にためしてみてはいかがでしょうか。
こちらの記事では、歯みがきの方法についてステップ別に詳しくご紹介。
はじめて歯磨きにチャレンジするという方や、猫が嫌がってなかなか歯磨きができないとお困りの方はぜひ参考にしてみてくださいね。
関連記事:すぐ実践できる!猫の歯磨きのやり方を3ステップでわかりやすく解説

予防3、サプリメントの使用
普段の生活の中で、さらに歯周病に気をつけたい飼い主さんにおすすめなのがサプリメント。
こちらの記事ではオススメのデンタルサプリメントについて詳しく書いていますので、気になる方はぜひ読んでみてくださいね。
関連記事:猫の歯肉炎予防にはデンタルバイオを!使って分かった嬉しい効果とは

こちらの記事で書かれているサプリメントを、ゆねにも試してみました。
ゆねも味を気に入ってるのか、パクパクと食べてくれています。もちろん、現在まで口の中のトラブルは0(ゼロ)です。
そのほかにも実感した効果については記事の中で詳しくご紹介していますよ。
予防4、歯周病予防効果のあるフードを選ぶ
実は猫の歯の健康のために作られたフードというものがあるんですよ。
一番の予防法としては、歯みがきを行ってあげることなのですが、今までしていなかった歯みがきをさせてくれる猫はそうそういません。
そんな方でも安心の、歯周病予防の出来るフードがあるんですよ。
ある程度の大きさと硬さがあるフードなので、フードを噛むことで歯の表面を擦ることになり、歯垢や歯石が付きにくくなります。
また、基本的にはドライフードなので、歯に詰まりにくく、そのため汚れも残りにくくなっているんです。
【歯肉炎を予防する4つの方法】
- ワクチン接種
- 歯みがき
- サプリメントを使う
- 歯周病予防効果のあるフードを選ぶ
歯肉炎を予防するための食事選び

歯肉炎と食事は切っても切り離せないもの。
そこで、先ほどご紹介したのが、歯周病予防効果のある餌(フード)への切り替え。
歯肉炎にならないようにと毎日の歯磨きを定着させるよりも、歯肉炎予防への一歩として、断然お手軽な方法です。
ここでは、歯肉炎予防効果の高い食事について、さらに詳しく説明していきますよ。
デンタルフード
デンタルフードとは、その名の通り『食べるだけでデンタルケアの効果があるフード』のこと。
ウェットフードを主食にしている猫の方が歯石の付着率が高く、付着の程度も強くなる傾向にあると言われています。
ドライフードの方が、歯に余分な食べかすが残りにくく、またよく噛むことで唾液の分泌が促進されるため、歯垢や歯石の予防効果も高いです。
また、免疫力が低下しているときに歯肉炎はなりやすいもの。年齢を重ねた猫はさらにそのリスクが高いと言えるでしょう。
免疫力の低下を防ぐために、しっかりと栄養の入ったフードを選びましょう。タンパク質含有率が30%以上あるものを目安に選べばバッチリ。
さらに、栄養面だけではなく、安全性の高いものを選ぶのもポイント。
「穀物類不使用・グレインフリー」と表記のあるフードを選ぶようにしましょう。
また、人工添加物が入っているものも避けるようにしましょう。
- 主食はウェットフードより歯石が付きにくいドライフードを選ぶ
- 免疫力維持のためにしっかりと栄養が入ったものを選ぶ(目安:タンパク含有率30%以上)
- 安全性の高いキャットフードを選ぶ(穀物と人工添加物が入っていないもの)
このフードは継続して食べることで効果が出るので、たまにあげるのではなく、一定期間は続けてあげるようにしましょう。
値段は一般のフードと比較すると高額になっています。
主食にすることが難しいようであれば、おやつに与えるなど工夫して、少しずつでも毎日食べ続けられるようにしましょう。
わたしも、愛猫ゆねにデンタルフードをあげ続けているのですが、ゆねは子猫の頃から食べ続けていたこともあり、残さずにしっかりと食べてくれていますよ。
食後の歯みがきもしているので、歯はとても丈夫でキレイだと自信をもって言えます。
最近は歯周病を気にする飼い主さんも増え、子猫や老猫でも食べることができるデンタルフードが増えているんですよ。
その中でもわたしも愛用している、おすすめフードを紹介したいと思います。
もし、フード選びで迷っている方がいらっしゃいましたら是非どうぞ。
関連記事:【まとめ】カナガンデンタルキャットフードを徹底調査!!口コミ&評判

関連記事:【まとめ】モグニャンキャットフードを徹底調査!【口コミ&評判】
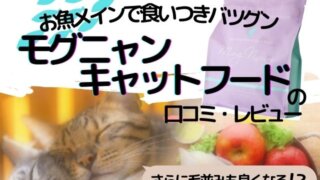
デンタルおやつ
デンタルおやつのほとんどは、ドライフード同様に硬さがあります。そのため、歯垢を付きにくくするだけでなく擦り落とす効果もあります。
種類によっては大きな粒のものもあるので、普段あまり噛まずに飲み込んでしまう猫もよく噛んで食べてくれます。
もちろん、おやつという名前の通り、味も美味しいものが多いです。
歯みがきを絶対拒否し、顔を触らせてくれない猫ちゃんや、おやつが大好きで毎日食べている猫ちゃんにはオススメ。
デンタルおやつにも種類がいくつかあります。
1.キブルタイプ
スナックタイプのおやつで、猫ちゃんにとってもスナック感覚で食べられるため、警戒心の高い子も喜んで食べてくれます。
粒も大きく、よく噛むことができ、味の種類も豊富です。
(2024/07/27 03:57:06時点 Amazon調べ-詳細)
2.ガムタイプ
犬のおやつとしても有名ですが、猫のおやつにもあります。
よく噛まないと飲み込めないため、噛む力がつき、口腔内の清潔を保つことができるようになります。
(2024/07/27 03:57:07時点 Amazon調べ-詳細)
3.ジャーキータイプ
この種類もデンタルケア用に加工されているものが多いです。
お肉を日干ししているため、嗜好性の高い猫ちゃんにオススメです。
(2024/07/27 15:15:42時点 Amazon調べ-詳細)
ペットショップなどで、様々なタイプのものが販売されていますので、猫ちゃんの好みにあったおやつを探してみて、スキンシップのお共に口腔ケアもいかがでしょうか。
歯の健康を気遣って作られたとはいっても、れっきとしたおやつです。与えすぎると肥満の原因に。適量を守り、また猫用ときちんと明記されているものを選ぶようにしましょう。
まとめ

今回の記事では歯肉炎についての知識やその予防についてお話ししました。
歯肉炎というのは、歯周病の初期段階で、きちんと治療をすれば正常な状態に回復する可能性のある段階でした。
早い段階で気づけるように歯肉炎の症状をしっかり覚えておきましょう。
【歯肉炎の症状】
- 歯肉の発赤、腫脹
- 口の痛み
- 口臭がきつくなる
- よだれが多くなる
- 口や顔に触られるのを嫌がる
- 食事中、頭を傾けたり、片側のみで食べている
- 食欲がなくなる(食べる量が減る)
そして歯肉炎になることで心配なのが、ご飯を食べなくなること。
歯肉炎の痛みで猫の食欲が落ちてしまったら次の方法を試してみてください。
【歯肉炎でご飯が食べられないときの5つの対処法】
- ドライフードからウェットフードへ変える
- ドライフードをお湯でふやかす
- お湯でふやかしたフードを食べないなら、猫の好きなもの(鶏肉、かつお節など)の煮汁でフードをふやかす
- ふやかしたフードをウェットフードとまぜる
- ミキサーを使ったり、すりつぶしたりして餌をドロドロにする
歯肉炎から歯周炎になってしまうと、口の中の痛さによって食事をとることもままならなくなり、どんどん弱っていってしまいます。
口の中が痛くても栄養状態を低下させないためには、飼い主さんの工夫が必要です。
大切な猫ちゃんがしっかりご飯を食べられるように、ぜひ試してみてくださいね。